Ⅰ.はじめに
長期休業の明けた直後や、新しい年度・学期の始まりは、子どもたちにとって大きな環境変化の時期です。
新しい友だち、先生、生活リズム──こうした変化は、子どもの心に少しずつ負担をかけます。
その負担が限界を超えると、子どもの心は折れてしまうことがあります。
そのため、周囲の大人が「いつもと違うサイン」に気づき、早めに支援の手を差し伸べることが何より大切です。
Ⅱ.子どもがSOSを発する場面とは
子どもが心のSOSを出す背景には、さまざまな状況があります。
- 身体的な危険:怪我、病気、災害など、命や安全に関わる体験をしたとき。
- 心理的なストレス:いじめ、虐待、強い叱責など、心が追い詰められる出来事があったとき。
- 学校での悩み:成績や友人関係、先生との関わりなどに不安を感じているとき。
- 家庭での不安:家族の不仲、離婚、病気、経済的な困難など、家庭環境の変化があったとき。
- 自分への否定感:自分が嫌い、自分に価値を感じない──そんな自己否定の気持ちが強くなっているとき。
これらのサインを早く見つけることが、子どもを守る第一歩です。
心が限界を迎える前に支援が届けば、回復に必要な時間もエネルギーも最小限にできます。
逆に、見逃してしまうと、子どもは長く苦しみ、時には大切な命が危険にさらされることもあります。
Ⅲ.保護者が気づくためのチェックリスト
日々の会話や生活の中で、次のような変化が見られないかを確認してみてください。
- 学校や家庭での出来事を、以前より話さなくなっていませんか?
- 眠れない、夜中に目が覚めるなど、睡眠の変化はありませんか?
- 「自分なんて…」と否定的な言葉が増えていませんか?
- 成績や興味への意欲が落ちていませんか?
- 友人関係で悩んでいそうな様子はありませんか?
- 家庭の雰囲気に敏感に反応していませんか?
- 食欲や体重の変化はありませんか?
- 自分や他人を傷つけるような発言や行動はありませんか?
これらのサインは「小さなSOS」かもしれません。
気になる変化が続くときは、子どもの話をじっくり聴き、必要に応じて学校や専門家に相談しましょう。
Ⅳ.子どもが安心して話せる環境を
- 話しやすい雰囲気をつくる:急に問い詰めるのではなく、「最近どう?」と優しく声をかけることから始めましょう。
- 専門家の支援を活用する:学校のスクールカウンセラーや地域の相談窓口に早めに相談することで、深刻化を防げます。
- 生活リズムを整える:食事・睡眠・運動など、日常の安定が心の安定につながります。
Ⅴ.子どもの心の変化を探る質問例
お子さんが自分の気持ちを言葉にできるように、こんな質問をしてみてください。
- 最近、不安になったり落ち込んだりしたことはある?
- 学校や家で、どんなときが楽しい?どんなときが嫌だと感じる?
- 最近、誰かに話したいことはある?
- 夜、よく眠れてる?
- イライラしたり怒りっぽくなることはある?
- 「自分が役に立たない」と思うことはある?
軽い話題から始め、少しずつ深い話に移ることで、子どもが安心して話せるようになります。
Ⅵ.支援が必要なサインを見逃さないために
次のような様子が見られたら、すぐに専門家へ相談してください。
- 自殺や自傷をほのめかす言葉がある。
- 学校に行けない、笑顔が減るなど、日常生活に支障が出ている。
- 心配な状態が2週間以上続いている。
相談先としては、小児科やスクールカウンセラー、地域の教育相談センターなどがあります。
「気のせいかも」と思っても、早めに相談することで、子どもの未来を守ることができます。
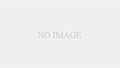
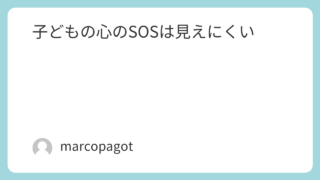

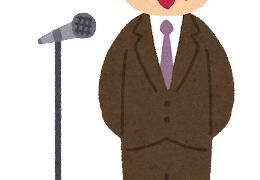
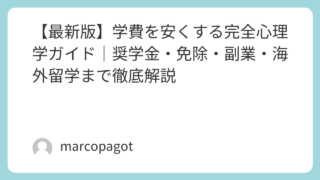


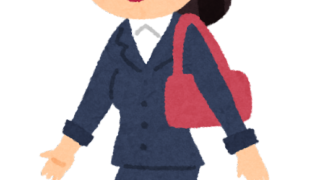
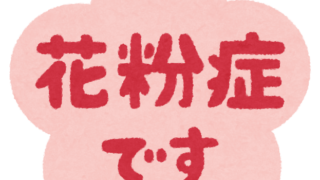
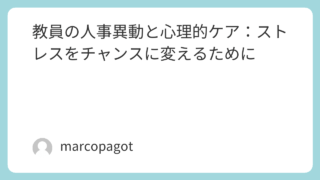

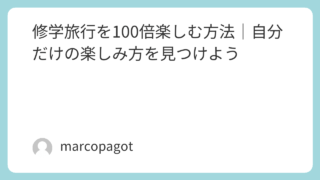
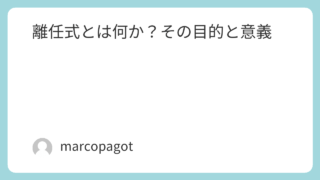

コメント