クラス替えは「人生のすべて」だと思う瞬間
新年度のスタート。昇降口や教室前に貼り出されるクラス名簿と担任発表は、子どもたちにとって一年を左右する大イベントです。
手が震えるほど緊張する子もいれば、泣き笑いの声が廊下に響くことも。
印刷配布か掲示か、あるいは放送か──。個人情報や安全面も考えつつ、学校ごとに方法を模索しています。
いずれにしても、あの瞬間は、まるで「小さな人生の分岐点」。
期待と不安が入り混じるあのざわめきこそ、新学期の象徴です。
担任ガチャという現実
クラス替えと同じくらい注目されるのが、「担任の先生発表」。
体育館のステージ上から見ていると、歓声とため息が交錯します。
「やったー!」と飛び上がるクラスもあれば、静かに肩を落とす子も。
その瞬間、ライブ会場のような空気が生まれます。
正直、見ていて微笑ましい。
でも、ステージ上の先生にとっては少し複雑です。
「しょっぱい顔された」と感じてしまえば、関係づくりの第一歩が難しくなることも。
そこで、最近は担任名も名簿と同時に通知し、過剰な盛り上がりを避ける学校も増えています。
ドラマの始まりと「感情の逆流」
子どもたちにとって、クラス替えはドラマです。
「同じクラスになれた」「嫌な子と一緒」「好きな子と離れた」──
その喜怒哀楽は本物です。
ただし時に、**「感情が先ではなく、行動が先」**になることがあります。
つまり、泣いてから悲しさを感じる。
「悲しい」というより、「悲しい自分を演じている」状態です。
脳と身体の連携が乱れ、感情のバグが起こる。
「うれしいのに怒る」「納得しているのに反抗する」など、矛盾した行動が生まれるのです。
そして時に、親子で“悲劇の主役”になり、学校への不満を膨らませてしまうことも──。
ここが、支援の分かれ道です。
マインドフルネスという受け止め方
そんなときに役立つのが、マインドフルネスの考え方。
「不快な感情を否定せず、そのまま認める」
「しかし、その感情に引きずられず、次に自分がすべきことに意識を戻す」
──この二つです。
「同じクラスになりたかった」「あの先生は苦手」
その気持ちは間違いではありません。
けれど、ずっとそこに留まっていては、次の一歩が見えなくなる。
人間関係は“相性”であり、すべての人と分かり合えるわけではありません。
それを知ることも、思春期の大切な学びです。
現実を見つめる力を育てよう
気の合わない友達や苦手な先生がいても、
一日のすべてを一緒に過ごすわけではありません。
たいていは授業の一部だけ。
その時間だけでも、「今この瞬間」に意識を戻せたら、それで十分です。
「嫌な気持ちを感じる=終わり」ではなく、
「そこからどう動くか=成長」なんです。
──そしてこれは、生徒だけの話ではありません。
教職員の世界にも、クラス替えはあります。
新しい職員室の空気に戸惑う先生方へ。
「気が合わない同僚がいても、今できる仕事に集中する」
それもまた、教育者としてのマインドフルネスです。
🪶 まとめ
クラス替えは、子どもにとって「小さな社会デビュー」。
うまくいかないと感じたときこそ、心を観察するチャンスです。
そして、誰もが“配られたカードで生きる”のが現実。
その中で、どう立ち上がるかを学ぶ一年にできたらいいですね。
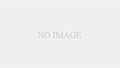
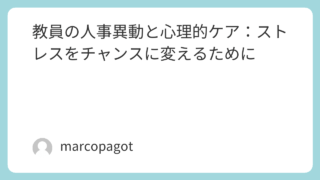
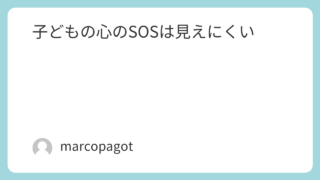
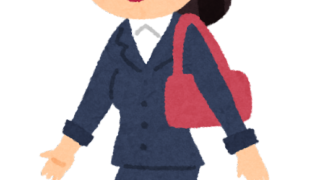

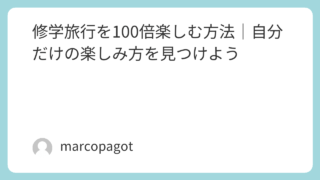
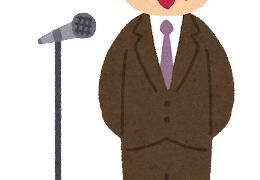
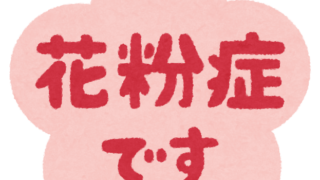

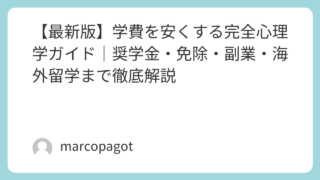
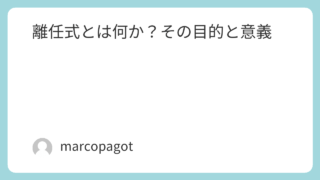



コメント