中学生が学校に行きたくなくなる理由
- パフォーマンスへの不安 中学校では成績やテスト、部活動など、評価される機会が増えます。その中で「うまくできない自分」が怖くなり、学校に行くこと自体が負担になることがあります。自分に自信を持てず、「頑張っても意味がない」と感じてしまうこともあります。
- 友達関係の悩み 友達との関係がうまくいかないと、教室が安心できる場所ではなくなってしまいます。クラス替えや人間関係の変化の中で、孤立感を覚えることもあります。中学生にとって「友達とのつながり」は、生活そのものに影響するほど大きなテーマです。
- 学校生活そのもののストレス 勉強内容の難化、課題の増加、部活動との両立…。中学生はいつも時間に追われています。「疲れがとれない」「気が休まらない」状態が続けば、当然ながら心が重くなっていきます。
- 家庭での環境変化 家の中での不安や緊張も、登校へのエネルギーを奪います。家庭内のトラブルだけでなく、親の忙しさやきょうだい関係の変化など、見えにくい要因が積み重なることもあります。
- 心のエネルギー不足 思春期には、誰でも一時的に心が疲れてしまうことがあります。落ち込みや不安が続いたとき、「学校に行きたくない」という形でSOSが出ることがあります。
中学生の心を整理するためにできること
- まず、話を聴く 子どもが何を感じているのかを、評価せずに聴くこと。それが最初の一歩です。 解決を急がず、子どもが自分の言葉で考え始められるよう、安心できる空気を作ることが大切です。
- 環境を整える 登校の方法や、教室での居場所づくりなど、物理的な工夫でハードルを下げることができます。 「朝は一緒に歩こうか」「好きな授業だけ行ってみようか」──そんな小さな調整が、再び動き出す力につながります。
- 学校と連携する 担任やスクールカウンセラー、養護教諭など、学校には多くの支援の仕組みがあります。 家庭だけで抱え込まず、情報を共有しながら、子どものペースで戻れる環境を整えていくことが大切です。
- 生活リズムを整える 食事・睡眠・運動という基本が、心の安定を支えます。体を整えることは、心を立て直す土台になります。
- 小さな成功体験を言葉で支える できたことを見逃さず、具体的に言葉で伝える。「昨日より元気そうだね」「自分で考えたんだね」――そんな一言が、子どもの自己効力感を育てます。
- 家庭の安心感を保つ 家庭は「失敗しても受け入れてもらえる場所」であることが何より大切です。 叱るよりも、寄り添う。子どもが心を休められる場があってこそ、次の一歩を踏み出せます。
- 必要なときは専門家へ 心の状態が深刻な場合には、専門のカウンセラーや医療機関につなぐことも大切です。 「相談する」こと自体が、支援の第一歩です。
子どもが学校に行きたくないと言ったときに
「どうして行けないの?」と問い詰める前に、「よく話してくれたね」と言ってあげてください。 中学生の「行きたくない」には、必ず何らかの理由があります。それは逃げではなく、今の力では支えきれない心の悲鳴かもしれません。
大人ができるのは、原因を一緒に探し、子どもが自分で立ち直っていける力を信じて支えること。
一時的な解決よりも、「自分の人生を自分で立て直せる力」を育てることを、私たちは目指したいのです。
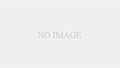
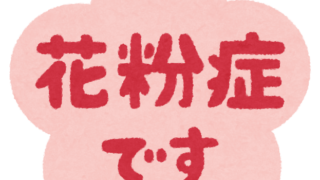
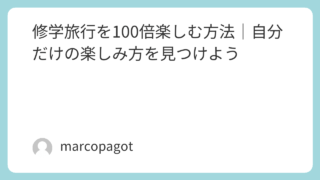
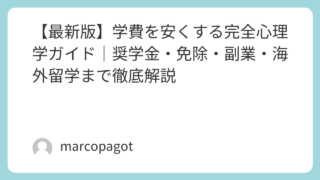
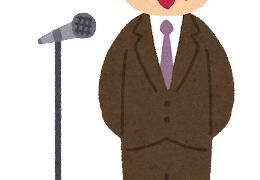


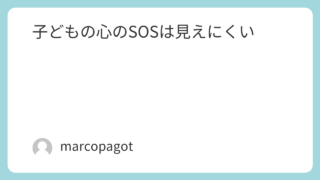

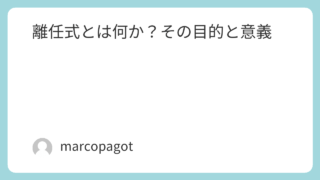
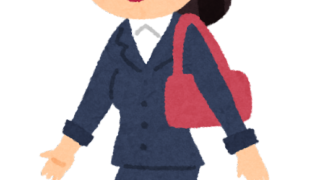

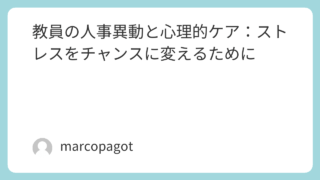

コメント