教員の人事異動と心理的ケア:ストレスをチャンスに変えるために
meta description: 教員の人事異動はストレスの大きい出来事ですが、心理的視点を取り入れることで自己成長の機会に変えられます。異動前後の準備・セルフケア・校内支援策を実例とともに解説します。
Ⅰ.教員の人事異動はいつ?
日本の公立学校では、年度末である3月下旬から4月初旬にかけて教員の人事異動が行われます。
各自治体の教育委員会が人事権を持ち、発表時期や手続きは都道府県によって異なります。
例えば、文部科学省の指針に基づき、
都道府県・市町村教育委員会は毎年度、職員の適正配置や人材育成を目的に人事異動を実施しています。
通常、3月末〜4月初めにかけて「離任式」や「着任式」が行われるのはこのためです。
教員にとっては、これまでの人間関係や職務内容をリセットし、新しい環境でスタートを切る節目となります。
Ⅱ.教員の異動がもたらす効果と心理的影響
【長所】
- 新しい環境での挑戦:異動により新しい教育文化に触れ、教員の資質向上政策の一環として専門性を高める機会になります。
- スキルアップ:新しい学習指導要領やICT活用教育に携わることで、教育実践の幅が広がります。
- 人間関係の再構築:異動先の職場で新たな人脈を築くことで、キャリアの視野が拡大します。
【短所】
- 家族の問題:転居や単身赴任が必要な場合、家族関係に心理的ストレスを生じます。
- 現場での適応困難:新しい文化・ルールへの適応には時間がかかり、最初の3ヶ月はストレス反応が出やすいとされています(参考:アメリカ心理学会(APA)職業適応研究)。
- 職場不一致のリスク:教育理念や管理方針が合わない場合、燃え尽き症候群(バーンアウト)の危険性も高まります(日本心理学会:教員バーンアウト研究)。
Ⅲ.異動前後の「心理的HACK」:ストレスを減らす実践法
① 異動前にやっておくべきこと
- 新しい勤務校の環境を下調べ(通勤・校舎・生徒層・校風)
- これまでの授業・業務を整理し、引継ぎ資料を作成(参考:岩手県教育委員会 引継ぎシートガイドブック)
- 自身の強み・弱みを分析し、次のキャリア目標を明確化
- 家族との生活リズム・通勤計画を調整し、生活基盤を安定化
② 異動後に意識すべきこと
- 最初の1ヶ月は「観察と吸収の期間」と捉える
- 小さな成功体験を記録し、自己効力感(Bandura, 1997)を高める
- 管理職・先輩教員に積極的に相談し、孤立を防ぐ
- 週ごとの「セルフケア日誌」で気分変動を記録し、早期疲労を察知
心理学的には、異動後3ヶ月以内に感じるストレスの約7割は「予期的不安」によるもので、
実際の職場環境よりも「まだ慣れていない自分」への焦りから生じると報告されています(出典:APA 2020: Stress and Uncertainty Study)。
Ⅳ.異動を「機会」に変えるために:心理学からの提案
教員の異動は避けられない制度ですが、視点を変えれば「自己再構築のチャンス」でもあります。
ストレスを完全に排除することはできませんが、注目の焦点を「失うもの」から「得るもの」にシフトするだけで、
感情反応が変化することが心理学的に示されています。
(参考:APA: Mindfulness and Cognitive Reframing)
もし疲労や気分の落ち込みが続く場合は、専門家との面談も選択肢の一つです。
教員向けのメンタルサポートとして、
国立特別支援教育総合研究所や、文科省 教職員メンタルヘルス支援策のページでは、各自治体の相談窓口が紹介されています。
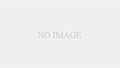
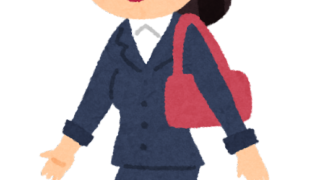
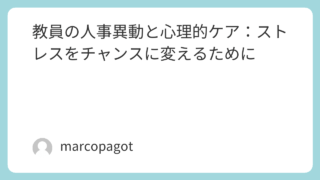

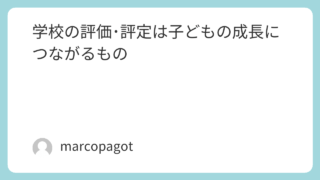

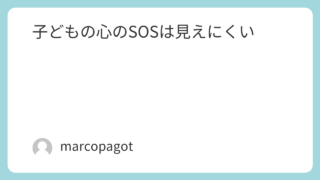
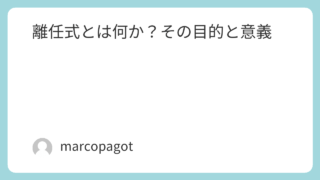
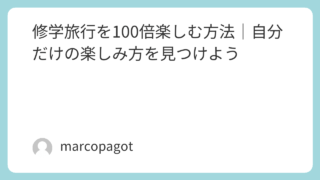

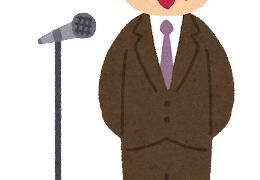
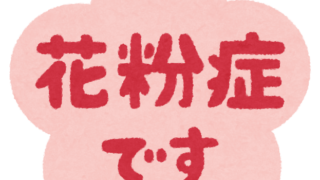
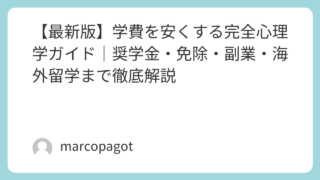

コメント